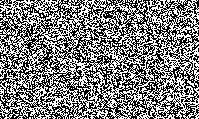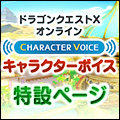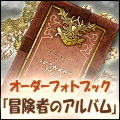カミリアの冒険日誌
2018-04-11 20:22:23.0 2018-04-11 20:25:14.0テーマ:その他
きょうの論点
明日、聖守護者の闘戦記が実装となります。
新運営は信用できるのか、新エンドコンテンツ実装時点で明らかになると昨年書きましたが、いよいよその時が来たわけです。
装備部位数以上の耐性を要求する既存コンテンツ型の敵が出てきた場合、白箱装備が集める労力の割に使えないということになり、運営はユーザーの意見を汲んでいるようで、そうではなかったということになります。
それ自体はさほど問題ではありません(どのみち、ユーザーの意見は程度問題こそあれ「あちらを立てればこちらが立たず」というトレードオフの関係にあるからです)。
ただし、自ら宣言したことも実行できない運営は「うそつき、またはコンテンツの制御能力がない」ということになるので、ユーザーの運営に対する心証は相当悪化します。
こちらのほうは、ゲームの存続に係る大問題です。
###
・・・ところで
これは、不可避の展開なのでしょうか。
そもそも、どうしてこうなっているのでしょう。
「創作者は、基本的に良い物を作ろうと思っている」
という前提のもと想像してみます。
ゲームはいくつもの要素が絡み合ってできています。
デベロッパー・ベンダー側からみると、予算や開発期間、稼働プラットフォームや想定ユーザー層。
プレイヤー側からみると、操作性や内容。
デベロッパー・ベンダー側の要素は制約要素であり、この範囲でよりプレイヤーに評価されるゲームを作ろうとします。
プレイヤー側の要素は、その結果に対する評価であるといえます。
原作物・シリーズ物は、既存のイメージを利用して想定ユーザーが買ってくれる確率を大幅に引き上げる代わりに、期待から大きく外れたことをすると評価に大ダメージを受けるという諸刃の剣のようなものです。
総じていえば新規につくるより容易なので、映画でもゲームでも開発にお金がかかるものほど、原作物・シリーズ物が多くなる傾向にあります。
DQXもまた、ドラクエというシリーズ物であるのは誰もが知っているところです。
キャラクターがリアルタイムに動き回って戦闘をするのに、コマンドメニューが出てくるという操作性もここに起因しています。
当初の稼働プラットフォームがwiiであったことから、必須回線速度や要求処理能力の都合上、ストリートファイターのようなオンライン格闘ゲームや、PUBGのようなアクションゲーム並みのシビアな応答性は実現困難だったでしょう。
また、シリーズ物としてドラクエの既存ファンを取りこぼしなく拾い上げるうえでも、指と眼を酷使しない方向へもっていく方が好都合だったはずです。
しかし誰もが無理なく操作できるということは、プレイヤー間の操作技量による差別化が困難であるということでもあります。
一方、ネットゲームの重要な訴求要素はプレイヤー間の差別化です。
身も蓋もない言い方をすると、他のプレイヤーより優位に立つためには、たくさん遊んでたくさんお金を落とす必要のある仕組みを作っておけば、あとは勝手にユーザー同士で競い合い、労せずして売り上げが伸びてゆくというのがネットゲームの営業的側面です。
差別化の要素は、大別して4つあります。
1.操作技量
2.知識・情報処理能力
3.支払額
4.プレイ時間
1は最初から望まれていませんでした。
2は想定ユーザー層の都合上、あまり作りこむことができません。
3も見た目(ドレスアップ)に限定するという方針のため、キャラクタースペックの差別化には使えません。
結果的に、プレイ時間でほぼすべてが決まる仕組みにせざるを得なかったという背景が見えてきます。
こうしてver1.x世代で、難易度=耐性(のある装備を買うための金策)という現在のルールが出来たのではないでしょうか。
しかし、それ以外の差別化要素が無かったことにより、耐性への過度な依存と急激な要素の消費が発生しました。
耐性装備の生産コストが平均的キャラクターの金策能力を上回り、最新装備の耐性を維持できなくなったプレイヤーから不満が出るとともに、
耐性の装備限界数とボスの耐性要求数の差が詰まって耐性による難易度調整の限界が迫ってきたのです。
※ver3からのゴールドばら撒きは、おそらくこの問題への対処療法です。
これらのことから、以下の解答が導出されます。
Q1.どうしてこうなっているのか
A1.デベロッパー・ベンダー側から見ると、この選択は最適解であったといえる。
Q2.これは不可避の展開なのか
A2.選択した時点で決まっていた限界を迎えたという意味で不可避であった。
###
ゲームを構成する要素の一部が限界を迎えただけでは、ゲームが限界を迎えたことにはなりません。
要素の限界への対応結果としてプレイヤーに見捨てられた時、ゲームの限界(寿命)を迎えるのです。
新運営は信用できるのか、新エンドコンテンツ実装時点で明らかになると昨年書きましたが、いよいよその時が来たわけです。
装備部位数以上の耐性を要求する既存コンテンツ型の敵が出てきた場合、白箱装備が集める労力の割に使えないということになり、運営はユーザーの意見を汲んでいるようで、そうではなかったということになります。
それ自体はさほど問題ではありません(どのみち、ユーザーの意見は程度問題こそあれ「あちらを立てればこちらが立たず」というトレードオフの関係にあるからです)。
ただし、自ら宣言したことも実行できない運営は「うそつき、またはコンテンツの制御能力がない」ということになるので、ユーザーの運営に対する心証は相当悪化します。
こちらのほうは、ゲームの存続に係る大問題です。
###
・・・ところで
これは、不可避の展開なのでしょうか。
そもそも、どうしてこうなっているのでしょう。
「創作者は、基本的に良い物を作ろうと思っている」
という前提のもと想像してみます。
ゲームはいくつもの要素が絡み合ってできています。
デベロッパー・ベンダー側からみると、予算や開発期間、稼働プラットフォームや想定ユーザー層。
プレイヤー側からみると、操作性や内容。
デベロッパー・ベンダー側の要素は制約要素であり、この範囲でよりプレイヤーに評価されるゲームを作ろうとします。
プレイヤー側の要素は、その結果に対する評価であるといえます。
原作物・シリーズ物は、既存のイメージを利用して想定ユーザーが買ってくれる確率を大幅に引き上げる代わりに、期待から大きく外れたことをすると評価に大ダメージを受けるという諸刃の剣のようなものです。
総じていえば新規につくるより容易なので、映画でもゲームでも開発にお金がかかるものほど、原作物・シリーズ物が多くなる傾向にあります。
DQXもまた、ドラクエというシリーズ物であるのは誰もが知っているところです。
キャラクターがリアルタイムに動き回って戦闘をするのに、コマンドメニューが出てくるという操作性もここに起因しています。
当初の稼働プラットフォームがwiiであったことから、必須回線速度や要求処理能力の都合上、ストリートファイターのようなオンライン格闘ゲームや、PUBGのようなアクションゲーム並みのシビアな応答性は実現困難だったでしょう。
また、シリーズ物としてドラクエの既存ファンを取りこぼしなく拾い上げるうえでも、指と眼を酷使しない方向へもっていく方が好都合だったはずです。
しかし誰もが無理なく操作できるということは、プレイヤー間の操作技量による差別化が困難であるということでもあります。
一方、ネットゲームの重要な訴求要素はプレイヤー間の差別化です。
身も蓋もない言い方をすると、他のプレイヤーより優位に立つためには、たくさん遊んでたくさんお金を落とす必要のある仕組みを作っておけば、あとは勝手にユーザー同士で競い合い、労せずして売り上げが伸びてゆくというのがネットゲームの営業的側面です。
差別化の要素は、大別して4つあります。
1.操作技量
2.知識・情報処理能力
3.支払額
4.プレイ時間
1は最初から望まれていませんでした。
2は想定ユーザー層の都合上、あまり作りこむことができません。
3も見た目(ドレスアップ)に限定するという方針のため、キャラクタースペックの差別化には使えません。
結果的に、プレイ時間でほぼすべてが決まる仕組みにせざるを得なかったという背景が見えてきます。
こうしてver1.x世代で、難易度=耐性(のある装備を買うための金策)という現在のルールが出来たのではないでしょうか。
しかし、それ以外の差別化要素が無かったことにより、耐性への過度な依存と急激な要素の消費が発生しました。
耐性装備の生産コストが平均的キャラクターの金策能力を上回り、最新装備の耐性を維持できなくなったプレイヤーから不満が出るとともに、
耐性の装備限界数とボスの耐性要求数の差が詰まって耐性による難易度調整の限界が迫ってきたのです。
※ver3からのゴールドばら撒きは、おそらくこの問題への対処療法です。
これらのことから、以下の解答が導出されます。
Q1.どうしてこうなっているのか
A1.デベロッパー・ベンダー側から見ると、この選択は最適解であったといえる。
Q2.これは不可避の展開なのか
A2.選択した時点で決まっていた限界を迎えたという意味で不可避であった。
###
ゲームを構成する要素の一部が限界を迎えただけでは、ゲームが限界を迎えたことにはなりません。
要素の限界への対応結果としてプレイヤーに見捨てられた時、ゲームの限界(寿命)を迎えるのです。
いいね! 5 件