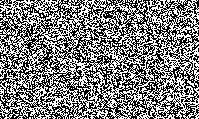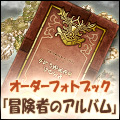はるこの冒険日誌
2016-08-16 13:36:59.0 2016-08-17 13:32:31.0テーマ:その他
夏休みの自由研究 ~阪急電車、阪神間モダニズム、小林一三~
昨日の日誌の続編です。
昨日の日誌でははいろいろ書きたいことが多すぎて、
主に面白の部分を大幅に割愛しなければならなかったので、
今日は面白を中心に書いていきたいと思います。
こんな豆知識があると火垂るの墓が10倍楽しくなる!
…かもしれない。www
<阪急電車>
関西ではお馴染みの小豆色の電車です。
あの色は正式にはマルーンといい、明治の開業以来若干色調の変化は
あるものの同じ色を使っています。
鉄道マニア的に「火垂るの墓」の阪急のシーンにツッコミを入れると、
・設定上は神戸線
・車両のデザインは京都線
・車内の雰囲気(狭さ)は宝塚線
という、「全部阪急だからいいじゃん」的なアバウトな感じになっています。
ただ、雑に作ったとまでは思っていません。
阪急神戸駅(→阪急三宮駅→現:阪急神戸三宮駅)や、車内から見える車窓の
風景は実景をもとに非常にリアルに描かれていますし、結果的には間違いでしたが
100形車両も正雀工場の保存車両を見に行ったのではないかと思われるほど
特徴をとらえて描かれています。
京都線100形車両は京阪傘下の新京阪鉄道が将来の名古屋、東京延伸をも視野に
非常に先進的な機構を取り込んだ名車として知られています。車両前面に付いた
大きな幌と直線を基調としたデザインは阪急というより京阪スタイルでした。
阪急電車は明治時代の終わりに大阪梅田と箕面、宝塚を結ぶ路線として
開業しましたが、当時の沿線は過疎地域であり、「狸か猪でも乗せるつもりか」
などと揶揄されることもあったとか。
専務である小林一三の才覚によって宝塚への娯楽施設の開設、池田をはじめとする
沿線の住宅開発が行われたことにより、利用客は順調に増加し、大正時代には
大阪神戸間の高速鉄道を開業。社名を阪神急行電鉄と改め、これが今日の「阪急」
の名前のルーツとなりました。
<阪神間モダニズム>
小林一三が分譲した住宅は、100坪の土地に一軒家というゆったりとしたもので、
サラリーマン層をターゲットにしたものでした。サラリーマンは多くの貯金は
持っていませんが、毎月安定した収入があることに目をつけ、日本最初とされる
住宅ローンによって住宅を販売しました。
こうした郊外住宅はその後の私鉄ビジネスひいては都市計画のモデルとして
現在に至るまで踏襲されているものです。
大阪と神戸の間にはこのようにしてできた住宅が立ち並び、主に高所得者の住居
として好まれるようになります。そうした住宅は現在のような機能的な台所など、
快適な生活を実現する設備を備えた先進的な住居でもありました。
スポーツやレジャーも盛んに行われるようになりました。
こうして生まれた生活様式は「阪神間モダニズム」と呼ばれるようになります。
「阪急」の高級イメージもこうした背景のもと生まれたものです。
「火垂るの墓」ラスト付近でお嬢様らしき少女たちが別荘と覚しきところへ
やってくる描写がありますが、西宮の山手にある苦楽園や隣接する六麓荘
(こちらは芦屋市)は別荘として開発されたものが高級住宅地へと変わっていった
地域であり、そういった事情をよく表していると思います。
<小林一三>
阪急の創業者小林一三はその才覚によって阪急を一大ブランドにまで育て上げた
人物ですが、彼は生活環境を改善することに積極的な考えを持つ人でもありました。
残念ながら長く続かなかったようですが、彼は分譲した住宅地で当時一般的では
なかった生協の立ち上げもしています。
(その後、やはり阪急沿線の灘で誕生したものが国内最大の生協として現存)
また、宝塚歌劇の産みの親でもあります。文学青年(実は当時は不良の代名詞でも
あったのだけれどwww)でもあった彼は歌劇の脚本を自ら手掛けたこともあった
とか。
生活者重視、文化志向という彼の思想が阪神間に先進的で文化的な居住空間を
作り上げたことは疑いようもなく、まさに阪神間モダニズムの立役者といって
よいでしょう。
そんな一三翁ですが、地下鉄が嫌いで都市内の鉄道は高架にすべし、という考えが
あったそうです。当時の常識として、「地下鉄は地震と水害に弱く高架は空襲に弱い」
とされていました。
もし、「災害は天からもたらされるもので、人の手で防ぎようもないが、空襲は
戦争さえ起こさなければ防ぐことができる」、という考えだったのだとしたら
とても素晴らしい考えだなぁ、と思うのですが…、
果たしてその辺りの実際のところは知る由もありません。
<参考文献>
戦前戦後にかけての阪急とその周辺の事情を知りたい方にはこんな本もあります。
「阪急電車青春物語」橋本 雅夫
本当に「面白」なネタも数多く収録されていますので、興味のある方はご覧下さい。
昨日の日誌でははいろいろ書きたいことが多すぎて、
主に面白の部分を大幅に割愛しなければならなかったので、
今日は面白を中心に書いていきたいと思います。
こんな豆知識があると火垂るの墓が10倍楽しくなる!
…かもしれない。www
<阪急電車>
関西ではお馴染みの小豆色の電車です。
あの色は正式にはマルーンといい、明治の開業以来若干色調の変化は
あるものの同じ色を使っています。
鉄道マニア的に「火垂るの墓」の阪急のシーンにツッコミを入れると、
・設定上は神戸線
・車両のデザインは京都線
・車内の雰囲気(狭さ)は宝塚線
という、「全部阪急だからいいじゃん」的なアバウトな感じになっています。
ただ、雑に作ったとまでは思っていません。
阪急神戸駅(→阪急三宮駅→現:阪急神戸三宮駅)や、車内から見える車窓の
風景は実景をもとに非常にリアルに描かれていますし、結果的には間違いでしたが
100形車両も正雀工場の保存車両を見に行ったのではないかと思われるほど
特徴をとらえて描かれています。
京都線100形車両は京阪傘下の新京阪鉄道が将来の名古屋、東京延伸をも視野に
非常に先進的な機構を取り込んだ名車として知られています。車両前面に付いた
大きな幌と直線を基調としたデザインは阪急というより京阪スタイルでした。
阪急電車は明治時代の終わりに大阪梅田と箕面、宝塚を結ぶ路線として
開業しましたが、当時の沿線は過疎地域であり、「狸か猪でも乗せるつもりか」
などと揶揄されることもあったとか。
専務である小林一三の才覚によって宝塚への娯楽施設の開設、池田をはじめとする
沿線の住宅開発が行われたことにより、利用客は順調に増加し、大正時代には
大阪神戸間の高速鉄道を開業。社名を阪神急行電鉄と改め、これが今日の「阪急」
の名前のルーツとなりました。
<阪神間モダニズム>
小林一三が分譲した住宅は、100坪の土地に一軒家というゆったりとしたもので、
サラリーマン層をターゲットにしたものでした。サラリーマンは多くの貯金は
持っていませんが、毎月安定した収入があることに目をつけ、日本最初とされる
住宅ローンによって住宅を販売しました。
こうした郊外住宅はその後の私鉄ビジネスひいては都市計画のモデルとして
現在に至るまで踏襲されているものです。
大阪と神戸の間にはこのようにしてできた住宅が立ち並び、主に高所得者の住居
として好まれるようになります。そうした住宅は現在のような機能的な台所など、
快適な生活を実現する設備を備えた先進的な住居でもありました。
スポーツやレジャーも盛んに行われるようになりました。
こうして生まれた生活様式は「阪神間モダニズム」と呼ばれるようになります。
「阪急」の高級イメージもこうした背景のもと生まれたものです。
「火垂るの墓」ラスト付近でお嬢様らしき少女たちが別荘と覚しきところへ
やってくる描写がありますが、西宮の山手にある苦楽園や隣接する六麓荘
(こちらは芦屋市)は別荘として開発されたものが高級住宅地へと変わっていった
地域であり、そういった事情をよく表していると思います。
<小林一三>
阪急の創業者小林一三はその才覚によって阪急を一大ブランドにまで育て上げた
人物ですが、彼は生活環境を改善することに積極的な考えを持つ人でもありました。
残念ながら長く続かなかったようですが、彼は分譲した住宅地で当時一般的では
なかった生協の立ち上げもしています。
(その後、やはり阪急沿線の灘で誕生したものが国内最大の生協として現存)
また、宝塚歌劇の産みの親でもあります。文学青年(実は当時は不良の代名詞でも
あったのだけれどwww)でもあった彼は歌劇の脚本を自ら手掛けたこともあった
とか。
生活者重視、文化志向という彼の思想が阪神間に先進的で文化的な居住空間を
作り上げたことは疑いようもなく、まさに阪神間モダニズムの立役者といって
よいでしょう。
そんな一三翁ですが、地下鉄が嫌いで都市内の鉄道は高架にすべし、という考えが
あったそうです。当時の常識として、「地下鉄は地震と水害に弱く高架は空襲に弱い」
とされていました。
もし、「災害は天からもたらされるもので、人の手で防ぎようもないが、空襲は
戦争さえ起こさなければ防ぐことができる」、という考えだったのだとしたら
とても素晴らしい考えだなぁ、と思うのですが…、
果たしてその辺りの実際のところは知る由もありません。
<参考文献>
戦前戦後にかけての阪急とその周辺の事情を知りたい方にはこんな本もあります。
「阪急電車青春物語」橋本 雅夫
本当に「面白」なネタも数多く収録されていますので、興味のある方はご覧下さい。
いいね! 14 件