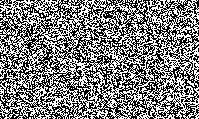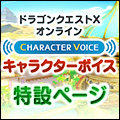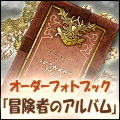フィンクの冒険日誌
2023-04-23 23:18:04.0 2023-04-23 23:46:53.0テーマ:その他
魔界地理学
人が生きていく為には、食べ物が必要である。
ドラクエXの場合、
それは、魔族であっても同様である。
さて、この現実世界を見てみると、
自ら食料を生産するのに適した地域もあれば、
そうでない地域もある。
例えば、砂漠や一部の海岸地域等は、
農産物を生産するのに適しているとは言えない。
だから、そういった地域に
暮らさざるを得ない人々は、
他の地域との交易によって、
農産物を手に入れるしかない。
農産物を手に入れられるかどうかは、
死活問題であり、
必然的に、
なり振り構わぬ、必死の交渉となる。
だから、
交渉術も長けてくるし、
考え方も柔軟になる。
港街に住む人々の内面性が、
開放的になるのは、その為でもある。
一方で、
自ら農産物を作る事の出来る地域では、
無理に交易をする必要もないので、
思考が段々と硬直的になる。
豊富な農産物を基に、
大国へと発展した場合、
それに輪をかけて、
面子を重んじるようになり、
相手に頭を下げてまで
取引をしようとは思わなくなっていく。
さて、では、ここまでの内容を、
V5の魔界に当てはめてみよう。
自国で農産物を作るのが難しく、
交易によって得るしかない砂漠地帯。
もちろん、ファラザードである。
自国で豊富な農産物を生産出来て、
無理に交易等しなくても、
自国で何でも完結出来てしまう森林地帯。
言うまでもなく、ゼクレスの事である。
ゼクレスの古くからの貴族達は、
思考が硬直化しており、変化を忌み嫌う。
伝統と格式を重んじると言えば聞こえは良いが、
大きな変化に対応するだけの力を持っていない。
永らく人々の内面に横たわり続けた旧態に、
アスバルが、うんざりしたのも無理はない。
一方の、ファラザードのユシュカは、
元々は、宝石商人の子供だった。
また後で述べるが、
間違いなく、その事が、
彼の内面に、大きな影響を与えている。

話は少しだけ変わるが、
「ありがとうの生まれた世界」で、
お金に備わる、
価値を価値のまま保存する役割について触れた。
ここでは、
価値と価値とを交換しやすくする役割について、
再確認をしたい。
あるところに、米農家がいたとしよう。
この米農家は、自分で作った米を、
魚と交換してもらう為に、漁師の所へ行った。
ところが、その漁師は、
自分が交換して欲しいのは、
米ではなくて肉だと言った。
原始的な物々交換の場合、
魚の欲しい米農家は、
米の欲しい漁師を探すしかなくなる。
ところがそこに、
お金というクッションを挟む事によって、
米 → お金 → 魚
という具合に、
価値と価値との交換がスムーズになるわけだ。
他者との取引には柔軟性が求められる。
なにせ、その相手は、
自分とは全く別の「個」だからだ。
だから、
そういった行為や経験を繰り返すうちに、
「一直線に欲しい物に辿り着かなくても、
繰り返して続けているうちに、
どこかで本当に必要な物が手に入る」、
という思考に至るのではないだろうか?
さて、思い返してみると、
ユシュカは、よく、
「取引」とか「交渉」という言葉を口にしていた。
砂漠で生まれ育ち、
宝石商人の子として交易で暮らしてきた、
そんな彼の、
これまでの人生が、その言葉から伺える。
魔界もアストルティアも、共に、
大魔瘴期という大きな障害に打ち当たる。
共通の課題、共通の敵を持つのであれば、
永らく対立してきた関係であっても、
そこに、
協力関係を築き上げるだけの余地が、
残されているのではないか?
そのような発想は、
彼の、それまでの経験抜きには考えられない。
地理的環境が、
人々の暮らしに影響を与え、
その暮らしの中にある、
行為や経験の積み重ねが、
人々の思考を形成していくのだ。
そんな背景に目を向け、
想像力を巡らせていく事が、
きっと、
他者を理解する事へと繋がっていくのだと思う。
ドラクエXの場合、
それは、魔族であっても同様である。
さて、この現実世界を見てみると、
自ら食料を生産するのに適した地域もあれば、
そうでない地域もある。
例えば、砂漠や一部の海岸地域等は、
農産物を生産するのに適しているとは言えない。
だから、そういった地域に
暮らさざるを得ない人々は、
他の地域との交易によって、
農産物を手に入れるしかない。
農産物を手に入れられるかどうかは、
死活問題であり、
必然的に、
なり振り構わぬ、必死の交渉となる。
だから、
交渉術も長けてくるし、
考え方も柔軟になる。
港街に住む人々の内面性が、
開放的になるのは、その為でもある。
一方で、
自ら農産物を作る事の出来る地域では、
無理に交易をする必要もないので、
思考が段々と硬直的になる。
豊富な農産物を基に、
大国へと発展した場合、
それに輪をかけて、
面子を重んじるようになり、
相手に頭を下げてまで
取引をしようとは思わなくなっていく。
さて、では、ここまでの内容を、
V5の魔界に当てはめてみよう。
自国で農産物を作るのが難しく、
交易によって得るしかない砂漠地帯。
もちろん、ファラザードである。
自国で豊富な農産物を生産出来て、
無理に交易等しなくても、
自国で何でも完結出来てしまう森林地帯。
言うまでもなく、ゼクレスの事である。
ゼクレスの古くからの貴族達は、
思考が硬直化しており、変化を忌み嫌う。
伝統と格式を重んじると言えば聞こえは良いが、
大きな変化に対応するだけの力を持っていない。
永らく人々の内面に横たわり続けた旧態に、
アスバルが、うんざりしたのも無理はない。
一方の、ファラザードのユシュカは、
元々は、宝石商人の子供だった。
また後で述べるが、
間違いなく、その事が、
彼の内面に、大きな影響を与えている。

話は少しだけ変わるが、
「ありがとうの生まれた世界」で、
お金に備わる、
価値を価値のまま保存する役割について触れた。
ここでは、
価値と価値とを交換しやすくする役割について、
再確認をしたい。
あるところに、米農家がいたとしよう。
この米農家は、自分で作った米を、
魚と交換してもらう為に、漁師の所へ行った。
ところが、その漁師は、
自分が交換して欲しいのは、
米ではなくて肉だと言った。
原始的な物々交換の場合、
魚の欲しい米農家は、
米の欲しい漁師を探すしかなくなる。
ところがそこに、
お金というクッションを挟む事によって、
米 → お金 → 魚
という具合に、
価値と価値との交換がスムーズになるわけだ。
他者との取引には柔軟性が求められる。
なにせ、その相手は、
自分とは全く別の「個」だからだ。
だから、
そういった行為や経験を繰り返すうちに、
「一直線に欲しい物に辿り着かなくても、
繰り返して続けているうちに、
どこかで本当に必要な物が手に入る」、
という思考に至るのではないだろうか?
さて、思い返してみると、
ユシュカは、よく、
「取引」とか「交渉」という言葉を口にしていた。
砂漠で生まれ育ち、
宝石商人の子として交易で暮らしてきた、
そんな彼の、
これまでの人生が、その言葉から伺える。
魔界もアストルティアも、共に、
大魔瘴期という大きな障害に打ち当たる。
共通の課題、共通の敵を持つのであれば、
永らく対立してきた関係であっても、
そこに、
協力関係を築き上げるだけの余地が、
残されているのではないか?
そのような発想は、
彼の、それまでの経験抜きには考えられない。
地理的環境が、
人々の暮らしに影響を与え、
その暮らしの中にある、
行為や経験の積み重ねが、
人々の思考を形成していくのだ。
そんな背景に目を向け、
想像力を巡らせていく事が、
きっと、
他者を理解する事へと繋がっていくのだと思う。
いいね! 30 件