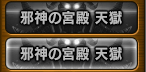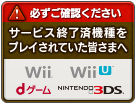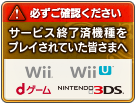ミラージュの冒険日誌
2013-09-18 01:19:38.0 テーマ:その他
なりきり冒険日誌~謎の半球体(1)
 夜の砂漠。冷たく乾いた空気が針のように肌を突き刺す。熱砂の地獄から氷の世界へ。砂漠の気候は、空が色を変えるより鮮やかに昼夜に入れ替わる。気候を安定させる水の力が弱いためである。
夜の砂漠。冷たく乾いた空気が針のように肌を突き刺す。熱砂の地獄から氷の世界へ。砂漠の気候は、空が色を変えるより鮮やかに昼夜に入れ替わる。気候を安定させる水の力が弱いためである。海の民と呼ばれ、常に水と共に暮らしてきた我々ウェディにとって、この変化の激しさは何度体験しても馴染めないものだ。
月明かりに照らされ、地平線の果てに見える影はカルサドラ火山。三闘像の特異なシルエットが闇夜に浮かび上がっている。
そして目の前に転がるのは巨大な半球体。幾何学模様に包まれ、その身の半ばを差中にうずめた奇妙なオブジェ。これが今回のお目当てである。
ガートラントでの一件が落ち着き、帰国した私に与えられた任務は、調査員たちに協力し、ドルワーム王国へと赴くことだった。
先だってアラグニで戦った、暴君と酷似した風貌を持つ魔獣、レオン・ビュブロ。彼奴についてより詳細な情報を得ようと、ドワチャッカのあらゆる情報が集まるドルワーム王立図書館に助力を請うのが目的だ。
幸か不幸か、王者の武具の一件で私の顔は割れている。交渉はすんなりと進むかに思われたのだが……
図書館中心部への立ち入りは予約制で、2か月先まで予定が埋まっているとのこと。どうしたものかと、首をひねっていた私の瞳に、悪戯めいた視線が飛び込んできた。
それがルルティマという年若い研究員との出会いだった。
 ドルワーム水晶宮。地下遺跡をもとに王城として再生されたこの巨大な宮殿は、神カラクリと呼ばれる不可思議な門により複雑に絡み合う迷路のような城である。
ドルワーム水晶宮。地下遺跡をもとに王城として再生されたこの巨大な宮殿は、神カラクリと呼ばれる不可思議な門により複雑に絡み合う迷路のような城である。床から壁、天井に至るまでびっしりと敷き詰められた幾何学模様にはドワーフたちの独特の美意識が見受けられる。青、赤、黄、緑と塗り分けられた絨毯にタペストリー。ともすればケバケバしくなりがちな色たちをくすんだ色調で統一し、上品にまとめたところがいかにもドワチャッカ風だ。
その一室、本来は兵士たちの休憩所として使用されるらしき部屋に通された私は、ルルティマから一つの取引を持ち掛けられた。
彼女の依頼を果たせば、明後日に迫った彼女の図書館使用権を譲ってくれるというのだ。
オマケもつけてあげるから、と茶目っ気たっぷりに片目をつぶる姿は研究員というお堅いイメージとは程遠いチャーミングなものだ。私はふと、ガタラに住むメンメの顔を思い出した。同じ研究員でも研究一筋でどこか浮世離れした彼女とは違い、ルルティマは社交的なタイプのようだ。
ともあれ、私にとっては渡りに舟だ。一も二もなく了承し、今に至る。
謎の半球体。ルルティマはこのオブジェをそう呼んだが、私には下半分が砂に埋まった鉄球に見える。
表面に描かれた幾何学模様は明らかに人工物だが、果たして誰が何のためにこんなものを作り、ここに放置したのか。門外漢の私にはさっぱりだ。
ドーム型の住居にも、何かの儀式に使う祭具にも見える。
周囲には同じ時代に作られたと思しきゴーレム達が眠っている。比喩ではなく、本当に眠っているのだ。近寄れば目を覚まし、襲い掛かってくるだろう。君子危うきに近寄らず。せめて言葉がしゃべれるなら、このシュールな鉄球について語ってもらうのだが。ゴーレムは黙して語らず。全ては沈黙の砂の彼方だ。
いくつかの半球体からもっとも大きなものを選び、サンプルを採取する。これにてお役目は終了。私はドルボードを起動した。
 夜のさざ波。冷たい砂の描く幾何学模様がドルボードの風圧に少し乱れ、やがて自然の形へと回帰する。ドルワーム王国への帰途、砂の海を駆けながら、私は足元に広がる広大な空間に思いを馳せていた。
夜のさざ波。冷たい砂の描く幾何学模様がドルボードの風圧に少し乱れ、やがて自然の形へと回帰する。ドルワーム王国への帰途、砂の海を駆けながら、私は足元に広がる広大な空間に思いを馳せていた。ゴブル砂漠の地下には、網の目のように張り巡らせた坑道が走っている。設置されたトロッコは今でも動くが、それを使う炭鉱夫たちの姿を、私は一度も見ていない。これが古代に使われていた炭鉱の慣れの果てなのか、今でも使われているのか、それすらよくわかっていない。
ただ、険しく広大な砂漠の地下に緻密な人工物が張り巡らされ、今もその命脈を絶やさず動き続けていることを思うと、文明のロマンとでもいうべきものを感じてしまう。
ドワチャッカはかつて機械技術により栄えた土地である、ということは誰もが知るところだが、何故、この地でのみ、そんな技術が栄えたのだろうか。
この砂漠を走っていると、答えがわかる気がする。
自然の恵みと共に生きる、というセリフは、まさに恵まれた土地に生きる者の言葉である。恵み乏しき砂の大地に、あるいは火山の懐に住むドワーフたちは、自然の驚異を技術の力でねじ伏せることでしか、生きられなかったのではないか。
門外漢による歴史考察など生兵法もいいところだが、直観的に私はそう思った。
やがて水晶宮の特徴的なシルエットが城壁の向こうに見え隠れする。
ルルティマが小さな首を長くして待っているだろう。
いいね! 18 件