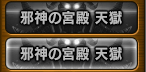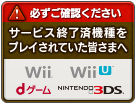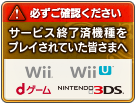ルキンフォーの冒険日誌
2021-09-01 18:42:25.0 テーマ:チーム紹介
これは、ボクの夏の思い出。
終業式の帰り、友人たちと別れて僕は海のある方へ自転車を進めた。
海に面したこの町は、海を目当てに観光客で混雑するような所ではなく、小さな港がある町。小高い山の中腹に僕の通う学校があり屋上からは町と海が一望できる。
海までに来たからと言って綺麗な景色があるわけでもなく、防波堤が続いている。小さいころはここに登ると地元の人によく怒られた。登っても怒られない場所を探したり、秘密基地とか作ったりもした。
そんな海沿いを自転車で漕いでいると、防波堤に誰かが立っているのが見えた。たぶん女の人だ。このあたりでは見慣れない雰囲気の女性だった。
黒く長い髪が風になびいて、雲の様に白い肌は眩しく、ソーダ水の様な色の空に溶けそうだった。
「ここの人ー?」
防波堤の上から風に乗って声が届いた。
遠くから見ると大人の女性だと思ってたが、近づくにつれて自分と同じぐらいだと思った。
「ねぇ、地元の人ー?」
また聞かれたので、自転車を止めて慌てて答えた。
「うん。地元だよ。」
「じゃーさー、こっち来て町のこと教えてくれない?」
そういうと、近くに寄って来た。
「学校も終わったんだし、ねーぇいいじゃん」
学生服を着てたらからそう思ったのかもしれない。
自転車のスタンドを立てて振り返ると、防波堤の上で彼女はしゃがみ込んでこちらに手を差し出していた。ちょうど目線の先に、彼女の胸元がチラっ見えたことで目を逸らした。そんな様子に彼女は気付くことはない。ただ彼女のペースに飲まれた。
出してもらった手を借りるわけには行かないから、彼女の少し横から上り防波堤に座り込んだ。
「あち!」7月も後半、太陽に照らされたコンクリートは熱く座るに躊躇するが、ここは気合で座って、海側に足を投げ出した。
一方彼女はハンカチを敷いているみたいで、足の向きは逆。道路側に足をブラブラしている。
「ねぇ、海の方向いてると、町のことわからないじゃん」
振り向くと彼女と初めて目があった。
大きくはっきりとした目、ややツンとした鼻、赤さがある唇には幼さがまだ残る。
彼女の顔を見惚れながら
「あぁ、そっか」と体を反転させる。
ここは車の通りも少なく、波の音が後ろから響く。
「あそこが、キミの学校?」
山の中腹にある学校を指差しながら、彼女は言う。
「うん。あれが高校」
「へぇー高校なんだ、ってことはキミ高校生なんだ。」
「うん。高1」
「あの学校、見晴らし良さそうだね?」
あまり学年とかには興味がなさそうだけど、続けた。「屋上からは町も海も見えるけど、普段は鍵がかかってる。」
「え!町も海も見えるなんていいなー。気持ちいいだろうなー」
相変わらず彼女のペース。
「ねぇあっちは?」
それから、一通り町を案内をした。駅や港。住宅地が多く、ちょっと離れたらショピングセンターもあるとか、それを楽しそうに聞いてた彼女の横顔には汗が滲み太陽でキラキラしてた。
時間にして10分も過ぎてないと思う。
「ヨっ!」と彼女は防波堤から飛び降りた。
「ねぇ、暑くなってきたし涼しいところまで連れてってよ。」
そう言うと、止めてあった自転車の後ろに座った。
「涼しいとところ?」
「そう!冷たいものとか飲みたいなー」
高校に行ってから行かなくなったけど、家とは反対の方向に駄菓子屋があるのを思い出した。小さい頃はよく通ったし、地元の小学生なんかはよく集まるお店がある。
「涼しいかわからないけど、駄菓子屋があるんだけど。そこでいい?」
そう尋ねると
「駄菓子屋!行ってみたい!」
無邪気に目を輝かせながら彼女は答えた。
僕も防波堤から降りた。
「カッコいい」と聞こえたような気もした。
彼女は一度自転車から降りて、スタンドを解除してくれた。
そして、僕に
「お願いします。」と自転車を渡した。
自転車にまたがると、「いい?」と確認しながら彼女は座わった。すると彼女の腕が僕の体を掴んだ。体が急に熱くなるのを感じて、太陽のジリジリした感じさえ失われていく。
「どうしたの?」気づかれたと思った。
「あっ、行くね。」と慌ててペダルに力を入れた。
自転車が進むにつれ、風が当たると本当は涼しいのに、体はとても熱く感じる。熱いことが彼女に伝わると思うと汗も滲む。
「ねぇ!重いのにごめんね。」と後ろから響く。
聞こえてる以上に、大きい声を出してるとわかる。
「ううん。平気だよ。」
「ありがとう。ここから、どれぐらいなの?」
「んー5分ぐらい!だけど、ゆっくり行くね。」
彼女を乗せて自転車を進める。たまに通る車は僕らを避けて横を通り過ぎていく、通るたびにギュッと体を掴まれる。まるで波に包まれるような感じがした。
この時、僕は初めて彼女の体温と感触を知った。
という風に「体温と感触」と言うチーム作りました。(たぶん続く

海に面したこの町は、海を目当てに観光客で混雑するような所ではなく、小さな港がある町。小高い山の中腹に僕の通う学校があり屋上からは町と海が一望できる。
海までに来たからと言って綺麗な景色があるわけでもなく、防波堤が続いている。小さいころはここに登ると地元の人によく怒られた。登っても怒られない場所を探したり、秘密基地とか作ったりもした。
そんな海沿いを自転車で漕いでいると、防波堤に誰かが立っているのが見えた。たぶん女の人だ。このあたりでは見慣れない雰囲気の女性だった。
黒く長い髪が風になびいて、雲の様に白い肌は眩しく、ソーダ水の様な色の空に溶けそうだった。
「ここの人ー?」
防波堤の上から風に乗って声が届いた。
遠くから見ると大人の女性だと思ってたが、近づくにつれて自分と同じぐらいだと思った。
「ねぇ、地元の人ー?」
また聞かれたので、自転車を止めて慌てて答えた。
「うん。地元だよ。」
「じゃーさー、こっち来て町のこと教えてくれない?」
そういうと、近くに寄って来た。
「学校も終わったんだし、ねーぇいいじゃん」
学生服を着てたらからそう思ったのかもしれない。
自転車のスタンドを立てて振り返ると、防波堤の上で彼女はしゃがみ込んでこちらに手を差し出していた。ちょうど目線の先に、彼女の胸元がチラっ見えたことで目を逸らした。そんな様子に彼女は気付くことはない。ただ彼女のペースに飲まれた。
出してもらった手を借りるわけには行かないから、彼女の少し横から上り防波堤に座り込んだ。
「あち!」7月も後半、太陽に照らされたコンクリートは熱く座るに躊躇するが、ここは気合で座って、海側に足を投げ出した。
一方彼女はハンカチを敷いているみたいで、足の向きは逆。道路側に足をブラブラしている。
「ねぇ、海の方向いてると、町のことわからないじゃん」
振り向くと彼女と初めて目があった。
大きくはっきりとした目、ややツンとした鼻、赤さがある唇には幼さがまだ残る。
彼女の顔を見惚れながら
「あぁ、そっか」と体を反転させる。
ここは車の通りも少なく、波の音が後ろから響く。
「あそこが、キミの学校?」
山の中腹にある学校を指差しながら、彼女は言う。
「うん。あれが高校」
「へぇー高校なんだ、ってことはキミ高校生なんだ。」
「うん。高1」
「あの学校、見晴らし良さそうだね?」
あまり学年とかには興味がなさそうだけど、続けた。「屋上からは町も海も見えるけど、普段は鍵がかかってる。」
「え!町も海も見えるなんていいなー。気持ちいいだろうなー」
相変わらず彼女のペース。
「ねぇあっちは?」
それから、一通り町を案内をした。駅や港。住宅地が多く、ちょっと離れたらショピングセンターもあるとか、それを楽しそうに聞いてた彼女の横顔には汗が滲み太陽でキラキラしてた。
時間にして10分も過ぎてないと思う。
「ヨっ!」と彼女は防波堤から飛び降りた。
「ねぇ、暑くなってきたし涼しいところまで連れてってよ。」
そう言うと、止めてあった自転車の後ろに座った。
「涼しいとところ?」
「そう!冷たいものとか飲みたいなー」
高校に行ってから行かなくなったけど、家とは反対の方向に駄菓子屋があるのを思い出した。小さい頃はよく通ったし、地元の小学生なんかはよく集まるお店がある。
「涼しいかわからないけど、駄菓子屋があるんだけど。そこでいい?」
そう尋ねると
「駄菓子屋!行ってみたい!」
無邪気に目を輝かせながら彼女は答えた。
僕も防波堤から降りた。
「カッコいい」と聞こえたような気もした。
彼女は一度自転車から降りて、スタンドを解除してくれた。
そして、僕に
「お願いします。」と自転車を渡した。
自転車にまたがると、「いい?」と確認しながら彼女は座わった。すると彼女の腕が僕の体を掴んだ。体が急に熱くなるのを感じて、太陽のジリジリした感じさえ失われていく。
「どうしたの?」気づかれたと思った。
「あっ、行くね。」と慌ててペダルに力を入れた。
自転車が進むにつれ、風が当たると本当は涼しいのに、体はとても熱く感じる。熱いことが彼女に伝わると思うと汗も滲む。
「ねぇ!重いのにごめんね。」と後ろから響く。
聞こえてる以上に、大きい声を出してるとわかる。
「ううん。平気だよ。」
「ありがとう。ここから、どれぐらいなの?」
「んー5分ぐらい!だけど、ゆっくり行くね。」
彼女を乗せて自転車を進める。たまに通る車は僕らを避けて横を通り過ぎていく、通るたびにギュッと体を掴まれる。まるで波に包まれるような感じがした。
この時、僕は初めて彼女の体温と感触を知った。
という風に「体温と感触」と言うチーム作りました。(たぶん続く

いいね! 30 件